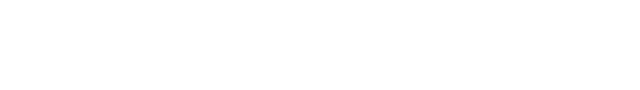エストロゲンを増やすには?|食事・運動・生活習慣の見直しポイントを解説
年齢を重ねるにつれて感じる体の変化に、不安や戸惑いを覚えていませんか。特に、女性ホルモンである「エストロゲン」の分泌低下は、更年期症状や肌の衰え、骨粗しょう症の発症リスク上昇など、さまざまな不調の引き金となります。エストロゲンは、女性の心身の健康を支えるうえで欠かせないホルモンです。
思春期以降は、女性らしい体型や肌のハリ・潤い、月経周期の調整に関わるほか、妊娠や出産にも大きく関与します。この記事では、エストロゲンの分泌をサポートする可能性のある食事・運動・生活習慣の工夫について解説します。
橋本駅南口から徒歩1分の長谷川レディースクリニックは、生理不順やPMS(月経前症候群)など、女性ならではの体調の変化に関するご相談はもちろん、男性不妊に関する検査や治療にも対応しています。専門医がお悩みに寄り添いながら、適切なサポートを提供いたします。
また、当院は神奈川県相模原市、淵野辺駅から徒歩2分のソフィアレディスクリニックと連携し、婦人科・不妊治療を提供しています。2つの施設間で検査結果や治療方針を連携・共有することで、より円滑な治療体制を実現しています。少しでも不安やお悩みを感じている方は、お気軽にご相談ください。
エストロゲンの基本知識
エストロゲンは、女性の美容や健康を維持するうえで欠かせない、代表的な女性ホルモンの一つです。分泌が不足すると、肌の乾燥、気分の不安定さ、生理周期の乱れなど、さまざまな不調が生じます。エストロゲンの基礎情報と重要性について、以下の項目に沿って解説します。
- エストロゲンの基本的な働き
- エストロゲン不足による症状
- エストロゲンが減少する主な原因
エストロゲンの基本的な働き
エストロゲンは、女性の体と心の健康を幅広く支える重要なホルモンです。生理や妊娠だけでなく、肌のハリやツヤの維持、骨密度の保持、血管の健康、気分の安定など、美容と健康の多方面に影響します。十分に分泌されることで、女性らしい体型や美しい肌を保ち、コレステロール値の調整や血管の柔軟性維持にも役立ちます。
逆に不足すると、肌の乾燥、髪の細り、気分の不安定さなどが現れ、更年期の不調の一因にもなります。
エストロゲン不足による症状
エストロゲンが不足すると、体と心の両面にさまざまな不調が生じます。特に40代以降は卵巣機能の低下により急激に減少し、更年期症状として表れることが多いです。若い世代でも過度なストレスや極端なダイエットによって不足する場合があります。具体的な症状は以下のとおりです。
- 生理不順
- のぼせ
- 発汗
- 肌の乾燥
- 髪のパサつき
- 骨密度の低下
- 気分の落ち込み
- イライラ
- 不眠
肩こりや腰痛、関節痛、疲労感といった身体症状に加え、長期的にはコレステロール値上昇や動脈硬化リスクも高まります。早めに症状を把握し、対策を取ることが大切です。
エストロゲンが減少する主な原因
減少の要因には、加齢と生活習慣の両方があります。加齢では30代後半から徐々に分泌量が減り始め、45~55歳頃の更年期に急減します。生活習慣による要因として、以下が挙げられます。
- 過度なストレス
- 極端なダイエット
- 喫煙
- 過度な飲酒
- 慢性的な睡眠不足
- 運動不足
特に、強いストレス下で働く女性や短期間で大幅に体重を落とした女性は、年齢に関係なくエストロゲンが減少することがあります。
エストロゲンを増やす食事と栄養
エストロゲンを増やすための食事と栄養は以下のとおりです。
- 大豆製品に含まれるイソフラボンの効果
- ビタミン・ミネラル豊富な食品を摂る
- 良質な脂質を摂取する
- バランスの良い食事でホルモンバランスを整える
大豆製品に含まれるイソフラボンの効果
大豆製品には、イソフラボンという成分が豊富に含まれています。イソフラボンは化学構造がエストロゲンと類似しており、体内でエストロゲンに似た作用を示すことから「植物性エストロゲン」とも呼ばれます。エストロゲンが不足しているときに、その働きを一部補う役割を果たすことが知られています。
イソフラボンを多く含む食品には、豆腐や納豆、味噌、きな粉など、日本の食卓になじみの深い食材がそろっています。毎日無理なく摂り続けられるよう、食事に工夫を取り入れましょう。日常生活に取り入れやすい一例は、以下の方法です。
- 朝食に納豆を添える
- 味噌汁に豆腐を加える
- おやつにきな粉入りの牛乳を楽しむ
ビタミン・ミネラル豊富な食品を摂る
ビタミンやミネラルが不足すると、エストロゲンの生成がスムーズに行われにくくなります。エストロゲンはコレステロールを原料として体内で作られますが、その変換過程には多くのビタミンやミネラルが関与しています。おすすめの食材として、緑黄色野菜、果物、海藻類が挙げられます。
緑黄色野菜はビタミンA・C・Eが豊富で、果物はビタミンCやカリウムを含みます。海藻類には鉄分やマグネシウムなどのミネラルが多く、鉄分はエストロゲン生成だけでなく赤血球の生成にも不可欠です。レバー、牡蠣、しじみなども積極的に取り入れましょう。
良質な脂質を摂取する
脂質は、エストロゲンの原料となるコレステロールを作るために欠かせない栄養素です。良質な脂質には、魚介類に多く含まれるオメガ3系脂肪酸や、ナッツ類やアボカドに含まれる不飽和脂肪酸があります。これらはコレステロール値を下げ、血流を改善する効果も期待できます。
揚げ物やインスタント食品などに多い飽和脂肪酸やトランス脂肪酸は、コレステロール値を上げ、血液の流れを悪化させる原因です。そのため、摂取を控えることが望ましいです。
バランスの良い食事でホルモンバランスを整える
食生活のリズムを整えることは、ホルモンバランスを維持するうえで重要です。炭水化物やタンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルをバランス良く摂取しましょう。主食・主菜・副菜をそろえることで栄養バランスが整いやすくなります。毎日同じ時間に3食をきちんと摂る習慣も大切です。
こうしたバランスの良い食事は、エストロゲンの分泌だけでなく、自律神経や免疫機能の安定にもつながり、心身の健康維持に役立ちます。
エストロゲンを増やすための運動と生活習慣
エストロゲンを増やす運動と生活習慣は以下のとおりです。
- 適度な有酸素運動
- リズム運動や股関節運動
- 質の良い7〜8時間の睡眠
- ストレス軽減で自律神経を整える
適度な有酸素運動
適度な有酸素運動は、エストロゲンの分泌に好影響を与えると考えられています。運動によって血流が促進されることで、卵巣への血液供給が向上し、エストロゲンの産生を助ける可能性があります。閉経後の女性を対象とした研究でも、有酸素運動の継続により、エストロゲン減少に伴うインスリン作用の低下が改善されるとの報告があります。
ウォーキングやジョギング、水泳、サイクリングなど、自分に合って無理なく続けられる有酸素運動を選びましょう。目安としては1日30分、週3回以上が理想的です。息がやや弾む程度の運動強度がおすすめで、毎日少しずつでも続けることで、エストロゲン分泌の促進が期待できます。
リズム運動や股関節運動
リズム運動とは、一定のテンポで筋肉を動かす運動のことを指し、ヨガ、ピラティス、太極拳などが代表例です。これらの運動は自律神経の調整に役立ち、ホルモンバランスの改善やエストロゲン分泌のサポートが期待できます。
股関節を動かす運動もエストロゲン増加に有効とされます。股関節周辺には子宮や卵巣など、女性ホルモンに関わる重要な臓器が集まっています。スクワットやストレッチなど、股関節を意識的に動かすエクササイズを日常に取り入れてみましょう。
質の良い7〜8時間の睡眠
睡眠不足はホルモンバランスの乱れを引き起こす大きな要因です。エストロゲンは、睡眠中に分泌される成長ホルモンと深く関わっています。成長ホルモンは骨や筋肉の成長促進だけでなく、代謝の調整や免疫機能の維持など、多岐にわたる働きを担っています。
十分な睡眠をとることで成長ホルモンの分泌が活発になり、エストロゲンの分泌もスムーズになります。毎晩7〜8時間の睡眠を確保することを意識しましょう。さらに睡眠の質を高めるためには、以下のような行動を心がけてください。
- 寝る前にカフェインを摂らない
- リラックスできる環境を作る
- 寝る前にスマートフォンやパソコンの画面を見ない
- ぬるめのお風呂に入る
- 軽いストレッチを行う
実行できそうなことから、少しずつ睡眠習慣を改善しましょう。
ストレス軽減で自律神経を整える
ストレスは自律神経のバランスを乱し、ホルモン分泌に悪影響を及ぼします。特に、ストレスホルモンと呼ばれるコルチゾールが過剰に分泌されると、エストロゲンをはじめとする他のホルモン分泌が抑えられる可能性があります。
心身の健康を保つためにも、自分に合ったストレス解消法を見つけることが大切です。自分なりのストレス解消法には、以下の方法を取り入れるのも効果が期待できます。
- 趣味に没頭する
- リラックスできる音楽を聴く
- アロマを焚く
- 自然の中で過ごす
- 友人や家族と過ごす
- ペットと触れ合う
- 軽い運動やストレッチ
自律神経が整うことによって、ホルモンバランスも整い、エストロゲンの分泌が促されます。
エストロゲンを増やすための医療的アプローチ
エストロゲンを増やすための医療的アプローチは以下のとおりです。
- ホルモン補充療法(HRT)
- 排卵誘発剤によるエストロゲン分泌促進
- 漢方薬
ホルモン補充療法(HRT)
ホルモン補充療法(HRT)は、体内で不足しているエストロゲンを補うことで、更年期障害の症状緩和や骨粗しょう症予防が期待される治療法です。治療方法には、内服薬や貼付薬、塗布薬などがあり、症状や生活スタイルに合わせて適切なタイプが選択されます。
HRTには、子宮体がんや乳がん、血栓症などのリスク増加が指摘されています。そのため、多くの場合はエストロゲン単独ではなく、プロゲステロンを併用した治療が行われます。子宮筋腫はエストロゲンの影響で増大する可能性があり、子宮筋腫を有する患者では実施の可否を慎重に検討する必要があります。
排卵誘発剤によるエストロゲン分泌促進
排卵誘発剤は、排卵を促すことでエストロゲンの分泌を高める薬剤です。主に不妊治療に用いられますが、エストロゲン増加を目的として処方される場合もあります。薬剤の種類には内服薬や注射薬があり、患者の症状や体調に応じて最適なものが選ばれます。
ただし、排卵誘発剤はエストロゲン分泌を増やす効果がある一方で、卵巣過剰刺激症候群(OHSS)などの副作用を引き起こす可能性があります。OHSSでは卵巣が腫れ、腹痛、吐き気、嘔吐といった症状が見られます。重症化すると呼吸困難や腎不全など、生命に関わる合併症を伴うこともあります。
安全に使用するためには、適切な投与量と使用期間を守ることが不可欠です。
漢方薬
漢方薬は、自然由来の生薬を組み合わせて行う治療法です。エストロゲンを直接的に増加させる作用はありませんが、ホルモンバランスを整え、更年期障害の症状緩和が期待できる処方もあります。体質や症状に応じて、最適な漢方薬が選ばれます。
副作用は比較的少ないとされますが、効果は緩やかで即効性は期待できません。体質によっては吐き気や下痢などの症状が現れることもあり、また他の薬との相互作用が生じる可能性もあります。そのため、使用前には必ず医師や薬剤師に相談することが大切です。
治療を選択する際は、メリットだけでなくデメリットも理解したうえで、医師と十分に話し合い、自分の状況に合った方法を検討しましょう。
年代別のエストロゲン対策
女性のエストロゲン分泌量は年齢とともに変動するため、各年代に合わせた適切なケアが重要です。20〜30代は分泌量が最も多い時期ですが、現代の生活習慣やストレスによりホルモンバランスが乱れやすい傾向があります。40〜50代の更年期には分泌量が急激に減少し、心身の不調が現れやすくなります。
60代以降は、加齢に伴う変化に合わせた新たなケア方法が求められます。ここでは、年代ごとのエストロゲン対策について詳しく解説します。
- 20〜30代のエストロゲン対策
- 40〜50代のエストロゲン対策
- 60代以降のエストロゲン対策
20〜30代のエストロゲン対策
20〜30代は、将来のホルモンバランスの土台を築く大切な時期です。現代の生活環境ではストレスや不規則な生活により、若くてもホルモンバランスが崩れやすくなります。正しい生活習慣を身につけることで、将来の更年期症状を軽減できる可能性があります。
妊娠や出産を視野に入れている女性にとっても、エストロゲンバランスの維持は重要です。バランスの良い食事や適度な運動、十分な睡眠を基本に、ストレス管理を行いましょう。例えば、以下の行動を習慣化しましょう。
- 週3回のウォーキング
- 1日7時間以上の睡眠
- 大豆製品を取り入れた和食中心の食生活
- 月経周期の記録
過度なダイエットは避け、適正体重を保つことも大切です。忙しい日々の中でも、意識的にリラックスする時間を確保し、趣味や友人との交流を楽しむことが心身の健康維持につながります。
40〜50代のエストロゲン対策
40〜50代は、更年期に向けてエストロゲンが急激に減少し始める時期で、丁寧なケアが欠かせません。この年代では卵巣機能が徐々に低下し、エストロゲン分泌が不安定になりやすいです。のぼせや発汗、イライラ、不眠などの更年期症状が現れやすく、日常生活に影響を及ぼすこともあります。
骨密度の低下や動脈硬化のリスクも高まるため、総合的な健康管理が重要です。食事面では、大豆製品を積極的に摂取し、カルシウムやビタミンDを多く含む食品を取り入れましょう。例として、朝は味噌汁、昼は豆腐サラダ、夜は納豆といった工夫が挙げられます。
運動面では、骨密度維持のための軽い筋力トレーニングと、ストレス緩和につながるヨガや水泳などの有酸素運動をおすすめします。症状がつらい場合は、我慢せず婦人科で相談し、必要に応じてホルモン補充療法や漢方薬の活用も検討しましょう。
60代以降のエストロゲン対策
60代以降は、卵巣からのエストロゲン分泌がほぼ停止するため、新たな視点でのケアが求められます。この時期は、副腎や脂肪組織からのわずかなエストロゲン産生を支えることが重要です。同時に骨粗しょう症や心疾患などのリスクが高まるため、予防的な健康管理に力を入れる必要があります。
食事面では、抗酸化作用の高い野菜や果物を多く取り入れ、魚や豆類など良質なタンパク質を意識して摂取しましょう。色とりどりの野菜サラダ、魚料理、豆料理などがおすすめです。運動は無理のない範囲で継続し、散歩やガーデニングなど楽しみながら行える活動を選ぶと続けやすくなります。
定期的に骨密度検査や健康診断を受け、必要に応じて医師と相談しながらサプリメントの利用も検討しましょう。社会とのつながりを保ち、趣味やボランティア活動などで生きがいを見つけることも、心身の健康維持に役立ちます。適切なケアを続けることで、60代以降も健康で充実した日々を送ることができます。
まとめ
エストロゲンは、女性の健康を支えるうえで欠かせない重要なホルモンです。加齢とともに分泌量は徐々に減少し、特に40代後半〜50代前半にかけて閉経を迎える時期には、その減少が顕著になります。これに伴い、更年期障害をはじめとする多くの不調が現れることがあります。
エストロゲンを増やすには、栄養バランスの良い食事や適度な運動といった日常的な生活習慣の工夫が重要です。更年期症状がつらい場合は、医療機関への相談も視野に入れましょう。
治療法としては、HRT(ホルモン補充療法)や排卵誘発剤、漢方薬などがあり、エストロゲン増加の可能性が期待されます。医師と十分に話し合い、自分に合った方法を選択することが大切です。
参考文献
Kawakami M, Yokota‑Nakagi N, Takamata A, Morimoto K. Endurance running exercise is an effective alternative to estradiol replacement for restoring hyperglycemia through TBC1D1/GLUT4 pathway in skeletal muscle of ovariectomized rats. J Physiol Sci, 2019, 69(6), p.1029‑1040.